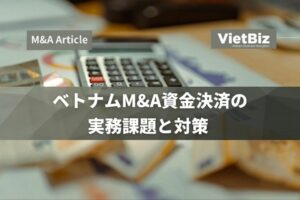ベトナムにおける工業団地のM&A最新動向と企業事例

目次
はじめに
米中貿易摩擦や地政学リスクの高まりを背景に、グローバルサプライチェーンの再編が加速する中、「チャイナ・プラスワン」の最有力候補としてベトナムが世界の注目を集めている。安定した経済成長、豊富な労働力、そして政府の積極的な外資誘致策を背景に、製造業の生産拠点としてベトナムの重要性は増すばかりである。
その生産活動の中核を担うのが「工業団地」である。旺盛な需要を背景に、既存の工業団地は高い稼働率を維持し、新たな開発も活発化している。こうした状況下で、日系企業がベトナムへ迅速かつ効率的に進出する手段として、工業団地開発会社や既存の工業団地を対象としたM&A(企業の合併・買収)が極めて有効な選択肢となっている。
本記事では、ベトナムの工業団地市場の最新動向を解説するとともに、M&Aを活用するメリットや、検討する上で留意すべき課題・リスクについて詳しく掘り下げていく。

ベトナム工業団地の市場動向
好調な外国直接投資(FDI)と高い稼働率
ベトナム経済の魅力と安定性を背景に、外国直接投資(FDI)は堅調に推移している。2024年に入ってもその勢いは続いており、特に製造業がFDI全体の大きな割合を占めている。この旺盛な投資の受け皿となっているのが工業団地であり、2024年7月時点で全国に429ヵ所、総面積は約13万ヘクタール以上に達している。主要な工業団地の平均入居率は80%を超え、特に南部のドンナイ省やビンズオン省では90%を超える高い水準で推移しており、供給が需要に追いついていない状況も見られる。
政府主導のインフラ開発と新たなトレンド
ベトナム政府は、経済成長を支えるインフラ開発を積極的に推進している。高速道路網の整備や、ラックフェン港などの大規模港湾の拡張は、国内の物流効率を飛躍的に向上させ、工業団地の魅力をさらに高めている。
また、近年では環境への配慮と持続可能性が世界的な潮流となる中、ベトナムでも「エコ工業団地」や「スマート工業団地」への関心が高まっている。政府は政令を通じてエコ工業団地の基準を定め、再生可能エネルギーの利用や廃棄物リサイクルなどを推進しており、環境基準を重視する外資企業にとって新たな投資インセンティブとなっている。実際に、国連工業開発機関(UNIDO)の支援のもと、既存の工業団地をエコ工業団地へ転換するプロジェクトも進行中である。

グローバル・ミニマム課税導入の影響
2024年1月からベトナムでもグローバル・ミニマム課税が導入された。これにより、これまで工業団地に進出する企業が享受してきた法人税の優遇措置の魅力が、一部の大企業にとっては相対的に低下する可能性がある。一方でベトナム政府は、税制優遇に代わる新たな投資支援策として、補助金の支給や土地使用料の減免などを検討しており、今後は税制以外のインセンティブの重要性が増していくと考えられる。
ベトナム工業団地のM&A 動向
不動産M&A市場における中核的な存在
ベトナムのM&A市場において、不動産セクターは常に取引額の上位を占める活発な分野である。中でも工業団地および物流施設は、製造業の拡大とeコマース市場の急成長を背景に、海外投資家から最も注目されるアセットクラスの一つとなっている。
シンガポール、韓国、台湾、そして日本など、多様な国の投資家が積極的に市場へ参入している。M&Aの手法も、工業団地開発会社の株式取得、特定の工業団地プロジェクトの買収、現地デベロッパーとの合弁事業設立など多岐にわたる。例えば2023年には、アジア太平洋地域の大手資産運用会社ESRグループが、BWインダストリアル社の株式を追加取得する大型案件があった。
日系企業も例外ではなく、丸紅が2024年にタイのアマタグループが開発するクアンニン省の工業団地事業に参画したほか、住友商事もタインホア省で4カ所目となる工業団地開発の承認を得るなど、積極的な動きが目立つ。

ベトナム工業団地におけるM&Aのメリット
土地・プロジェクト取得の迅速化
新規で工業団地を開発する場合、土地収用から開発許可の取得までに数年を要することも珍しくない。M&Aを活用すれば、既に許認可を取得済みのプロジェクトや稼働中の工業団地を一括で取得できるため、事業開始までのリードタイムを大幅に短縮できる。これは、サプライチェーン再編など、迅速な意思決定が求められる現在のビジネス環境において大きな利点となる。
既存インフラとローカルネットワークの活用
M&Aにより、電力、水道、道路、通信といった整備済みのインフラをすぐに利用できる。また、既に入居しているテナントとの契約を引き継ぐことで、買収初日から安定した収益を見込むことも可能である。さらに、現地パートナー企業が長年かけて築き上げてきた行政機関や地域社会との良好な関係性(ローカルネットワーク)を活用できる点も、事業運営を円滑に進める上で非常に重要である。
付加価値創造による資産価値向上
既存の工業団地を取得後、日本の優れた環境技術やデジタル技術を導入し、「エコ工業団地」や「スマート工業団地」へとアップグレードすることで、新たな付加価値を創造できる。これにより、テナント誘致における競争力を高め、賃料収入の増加や資産価値そのものの向上を図ることが可能である。
ベトナム工業団地におけるM&Aの課題・リスク
法務デューデリジェンスの複雑性
ベトナムでは外国企業による土地の「所有」は認められておらず、「土地使用権」を取得する形となる。この土地使用権の有効期間や各種条件、政府のマスタープランとの整合性など、法務面で精査すべき項目は多岐にわたる。地方政府ごとに規制の解釈や運用が異なる場合もあり、専門家による詳細なデューデリジェンスが不可欠である。
インフラの老朽化と追加投資リスク
開発から年数が経過した工業団地の場合、道路や排水設備、電力供給システムなどが老朽化している可能性がある。買収後に想定外の大規模修繕や追加投資が必要となるリスクを避けるため、物理的なデューデリジェンスを通じてインフラの状態を正確に把握する必要がある。
潜在的な環境汚染リスク
過去の入居企業の操業に起因する土壌汚染や水質汚濁といった環境問題が、買収後に発覚するケースも考えられる。環境デューデリジェンスを徹底し、汚染の有無や浄化義務の所在を明確にすることが極めて重要である。
適正な企業価値評価の難しさ
好調な市場を背景に、売り手側の期待する価格が高騰している傾向がある。売り手と買い手の価格ギャップが交渉の障壁となることも少なくない。客観的なデータに基づいた事業性評価(バリュエーション)を行い、買収価格の妥当性を慎重に見極める必要がある。

工業団地業界の代表的企業
Becamex IDC Corporation(ベカメックス)
ベトナム南部ビンズオン省を拠点とする国内最大級の工業団地開発会社の一つである。1976年の設立以来、45年以上にわたって工業団地・都市開発事業を手がけ、現在までに15ヵ所の工業団地を開発・運営している。総開発面積は約1万5000ヘクタールに達し、サムスン、トヨタなど世界的な製造業大手が入居している。近年はスマートシティ開発にも注力し、住友林業やNTT都市開発との大型合弁プロジェクトでも知られている。2024年の売上高は約8億ドルを記録している。
Long Hau Industrial Park Investment Company Limited(ロンハウ工業団地)
ホーチミン市近郊のカントー省に拠点を置く工業団地開発・運営会社である。ベトナム南部の重要な工業拠点であるロンハウ工業団地(総面積1,100ヘクタール)の開発・管理を主力事業とする。同工業団地は入居率95%以上を維持し、日系企業を含む200社以上が操業している。特に食品加工、電子部品、繊維業界の企業が多く、輸出志向の製造業にとって戦略的な立地となっている。環境配慮型の工業団地運営にも力を入れ、廃水処理システムの高度化などでUNIDOの認証も取得している。

工業団地業界のM&A事例
ESRグループによるBW Industrial Development株式追加取得(2023年)
アジア太平洋地域最大級の物流・工業不動産デベロッパーのESRグループが、ベトナムの工業団地開発会社BW Industrial Development社の株式を追加取得し、持株比率を85%まで引き上げた大型M&A案件である。取引総額は約4億5000万ドルに達し、ベトナム工業団地セクターにおける過去最大級の取引となった。この買収により、ESRはハノイ・ホーチミン周辺の主要工業団地8カ所、総面積3,200ヘクタールを統合管理することとなり、ベトナム市場でのリーディングポジションを確立した。買収後は日本・韓国・台湾企業を中心としたテナント誘致を強化し、稼働率は買収前の82%から92%まで向上している。
丸紅・Amata Vietnam合弁による工業団地開発案件(2024年)
丸紅がタイの工業団地大手Amataグループとの合弁により、クアンニン省で総開発面積1,800ヘクタールの大規模工業団地開発プロジェクトに参画した事例である。総投資額は約12億ドルで、丸紅が60%、Amata Vietnamが40%を出資する合弁会社を設立した。同プロジェクトは、中国国境に近い立地を活かした「チャイナ・プラスワン」の受け皿として位置づけられ、自動車部品、電子機器製造業を主要ターゲットとしている。開発は3期に分けて進められ、第1期(600ヘクタール)は2025年末の分譲開始を予定している。丸紅の日系企業ネットワークとAmataの工業団地開発・運営ノウハウを組み合わせた戦略的提携として注目されている。

まとめ
ベトナムの工業団地は、世界の生産拠点としての地位を確固たるものにしつつあり、今後も持続的な成長が期待される。日系企業にとって、M&Aは、この成長市場へ迅速に参入し、事業基盤を確立するための強力な手段となり得る。
一方で、法制度の複雑さや潜在的なリスクも存在するため、成功のためには信頼できる専門家の支援が不可欠である。現地の法務、財務、不動産に精通したパートナーと連携し、精緻なデューデリジェンスと周到な準備をもって臨むことが、ベトナムでのM&Aを成功に導き、中長期的な成長を実現する鍵となるだろう。